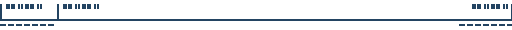
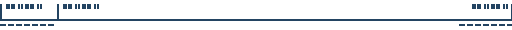


| 【米沢街道】 | 奥州街道の福島から分岐して板谷峠を越え、米沢を経て上山で羽州街道に合流した。福島側からは米沢街道、山形側からは羽州街道または最上街道とも呼んだ。福島から出て笹木野・庭坂・李平・板谷・大沢の各宿場を経て米沢に出た。 この街道は福島盆地と米沢盆地を支配していた伊達氏によって15世紀にひらかれ、戦国時代には米沢城の伊達政宗がこの街道によって中通りに進出したとされる。政宗のころは奥州街道八丁目宿(松川)を起点とし、大森・下村・庭坂を経て板谷峠に向かう道筋だったが、江戸時代に入って福島が起点となった。 板谷峠を越えるため難所の多い街道だったが、1613年(慶長18)には山間に李平宿がひらかれ、山間での宿場が可能になった。しかし明治時代に入って栗子峠を越える万世大路がひらかれたことから、米沢街道は旧道に転じた。 |
| 【万世大路】 | 古い米沢街道に代わり、1881年(明治14)に完成した道で、栗子峠を越えて福島と米沢を結ぶ。完成したとき東北ご旅行の明治天皇が通られ、万世大路と名付けた。現在は国道13号がこの道にとって代わった。 |
| 【羽州街道】 | 奥州街道の桑折から分岐して山形・秋田を経て青森に達した本街道に準ずる脇街道で、奥州の主要街道だった。桑折から分岐して小坂峠を越え、七ヶ宿を経て北上し、上山(山形県)へと出た。 |
| 【奥州街道】 | 正式には江戸から白河までを奥州街道と呼び、このうち宇都宮までは日光街道と一緒だった。白河から先は「奥州街道」「奥州道中」などとも呼び、千住−宇都宮−白河−福島−仙台−盛岡−青森三厩がその道筋で、江戸から白河までは幕府道中奉行、白河から先は同勘定奉行が支配していた。現在の国道4号はほぼこの街道に沿って北上している。 |
| 【中村街道】 | 奥州街道と相馬領を結ぶ相馬街道のうち、福島から掛田・行合道・玉野を経て中村に出た。現在の国道115号にあたる。なお掛田から月舘・川俣を経て二本松にも通じていた。 |
| 【浜街道】 | 水戸街道を水戸−勿来−平−原町−中村を経て岩沼(宮城県)で奥州街道に合流する道。一般には浜通り、陸前浜街道などとも呼ばれた。現在の国道6号もほぼ当時の道筋に沿っている。 |
