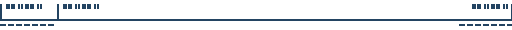
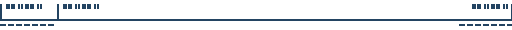
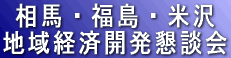
東北中央自動車道建設促進総決起大会
平成12年9月26日 福島市 福島テルサ
基調講演 『広域連携と道路整備の役割』 講 師 自由民主党 道路調査会会長 村岡兼造 氏 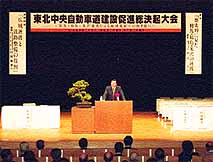 |
最近、公共事業はばら撒きであり、もうこれ以上道路はいらないという人がおります。しかし、公共事業は社会資本の整備として必要であるという考えもあります。地方の実情として、一番の要望は道路整備であり、国民に社会資本の道路の必要性というものを訴えていかなければなりません。 バブルの時は、予算も年々増えている時であり、「道路特定財源を一般財源に」というような議論は起きませんでした。しかし、バブルがはじけてから10年以上、予算も厳しい状況の中で、道路特定財源を道路にばかり使うのではなく、一般財源として使ったらどうかというのが今年の政府税調において出て、両論併記の答申が出されている状況です。 明治以来、河川・道路等の社会資本の整備が一番先にできたのは東京です。新幹線や高速道路、あるいは大学・美術館・博物館等いろいろなものがすべて東京一極集中でできました。だから、働く場所もでき、そして所得も増えていった。 ところで、道路の特定財源は、大体一年に6兆円入ってきます。自民党の中で亀井政調会長が道路特定財源を新幹線の整備に使いたいと考えておりますが、道路整備緊急措置法第3条において「揮発油税及び石油ガス税による収入は、道路整備費の財源に当てなければならない。」と規定されておりまして、これを新幹線の整備に使うというのは筋違いです。 道路特定財源制度の意義ですが、まず一つ目は「合理性」があること。自動車利用者の負担が道路整備に当てられることは、受益と負担の関係が明らかであります。二つ目は「公平性」があること。道路を利用する自動車は、すべて皆利用の大小に応じて費用を分担しています。三つ目は「安定性」であります。計画的な道路整備のため、必要な財源を毎年度安定的に確保できることです。道路特定財源の決着は年末に大きな山があると考えております。 平成13年度の建設省で出した全体事業費は7兆5千億円です。重点事項として、ETC普及促進によるIT社会実現の支援があります。整備目標としては、平成14年度までに全国の主要な900料金所でETCレーンが設置されます。都市高速道路においては、概ね5年後に完全ETC化を予定しています。また、交通円滑化対策、物流対策のスピードアップとして"あかずの踏切"対策の集中実施、あるいは都市の拠点となる駅前等の交通結節点の集中改善等が上げられています。 また、第四次全国総合開発計画では高規格幹線道路網について、1万4千キロで形成する事になっておりますが、現在供用を開始しているのは約7千キロです。東北地域もようやく建設が盛んになってきていますがまだまだこれからです。現在、道路調査会において7〜8人の議員を集め、阿武隈東道路等の国直轄事業をいかに早期に実施するかについての研究を年末ぐらいまでしていきたいと考えています。 道路ができることで人事交流、物資の交流等の広域連携が盛んになっています。福島県においても救急医療のネットワークが形成されたり、観光客が大幅に増加したと聞いております。今後は、未整備区間をいかに早期に整備を進めていくかということです。 道路建設においては、用地買収の難航、環境アセスメントの長期化等の問題もありますが、いずれも地元の皆様方の協力が必要であります。我々も道路財源の確保に一生懸命頑張りますので、皆様方にも是非ご協力を頂き、一日も早い高速道路網の整備・東北中央自動車道の完成に道路調査会長としても頑張っていきたいと思います。 |
